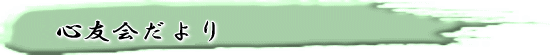 |
昭和47年10月28日
第34号
「おまつり」について
|
日頃の神様のご加護と御恩に感謝する秋の大祭をおごそかに、盛大に、かつにぎにぎしくとり行わせて頂けたことを心から大国様に感謝申し上げます。 今回は日ごろなにげなく使っている「おまつり」という言葉はどういうことなのかをじっくり考えてみようと思います。 普通「おまつり」というと、氏神様などの縁日の出店屋台のにぎわい、おみこしや山車行列のことを思い出すか、あるいは格式高い神社の何々祭という荘重な儀式のことを 思い出すことと思います。縁日のにぎわいも楽しみも、荘厳な儀式も「おまつり」ということの一面には違いありませんが、「おまつり」の本質はそんなところにはありません。 まず、「おまつり」の「まつる」と云う言葉は古い日本語で「よろこび服する」という意味の「まつろふ」と云う言葉から出ています。同系統の言葉に「まつわる」という言葉があります。 これは子供が親にしたい甘えて、する寄る様を言い表す場合などにふさわしい言葉です。 言葉の上からわかる通り、「神をおまつりする」ということは神から分霊を受け、神によって生かされている人間が、神をしたい寄って行き神の境地に帰らせていただくことに他なりません。 しかし、有限なる人間が無制限に無限で、絶対なる神の境地にまで還らせて頂けるはずはありません。神様にしたい寄りたいという人間の切なる気持ちを形にあらわしたのが、儀式としての祭りです。 儀式としての祭りはだいたい、1.修祓2.謝恩3.神意継承4.守護祈願5.玉串拝礼6.直会(なおらい)からなっています。 人間は日々知らず知らずの間に、罪や穢をつくっているものですが、神にしたい寄るに当って、したいよるにふさわしい罪穢のない人間となることを求められるのは当然です。 罪穢を祓うには、お祓の神々の御神力による祓と自分で行ずる(みそぎ)と自分と御神力とによる鎮魂とがあります。祭式の場合には普通、祓串に祓戸の大神の御神力をいただいて祓っていただき、 罪穢なき人間として、御神前に進ませていただくわけです。ここまで修祓というわけです。 それからまず、日ごろの神の御加護に感謝する祈りをささげ、次第次第に神の境地に帰らせていただき、神の御意志を自分の意志として受け継ぎ最後に行く末の守護を祈願する一連の 祝詞がつづくわけです。 これは私達が日ごろあげている神拝詞に言い尽くされていることです。つまり、「大神たちの高き尊き御恵の蔭に隠ろひ平らけく安けく有経る事を嬉しみ添なみ云々」という部分は まさに謝恩の詞であるわけです。 次に、神は世界の国々は平和であって欲しい、また各家庭はそれぞれ平安で、繁栄していって欲しい、人は各人なりわいを怠らず、人としての道理にたがわずやってほしいと 意志されているわけですが、各人がそういう神の御意志を受け継いで、そのように生活することが神意継承ということです。これは神拝詞の中程に書かれているとおりです。 最後に守護祈願は神拝詞の「為と為す事等をば云々」から終わりにかけて言い尽くされています。 以上が御祭りの本質、精神と云うものです。この祭りの神髄を形に表したものが玉串拝礼と直会です。 タマとは宝物という意味の玉ではなく、魂のことです。つまり、玉串とは神の分霊である自分の魂と神の霊とを串にさし通した形とみることもできます。そこに神意継承の精神が 象徴されているとも考えられますし、神と自分が一体であり、神が常々守っていて下さるという安心感の象徴とも考えられます。 その意味では直会も神人一体の観念を形に表したものだと言えます。つまり、直会とは神にお供えし、神がめしあがったと同じものを御神前で、神と一緒にいただき、神に帰一する ということを意味しています。 以上みてきたとおり、お祭りとは本来、明るく清い心ですなおに神にしたい寄っていき、神の御心に服して生活させて頂けるよう、身心をそのように神に振り向ける儀式のことなのです。 |
最新はこちらから
バックナンバー一覧に戻る
Copyright (C) 2000-2004 IzumoShinyuKyoukai Org. All Rights Reserved.